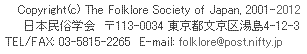HOME > 談話会開催記録 > 2010年 > 第849回 > A会場|B会場
談話会要旨-第849回(2009年度 民俗学関係修士論文発表会)B会場
古峰ヶ原信仰の研究?福島県郡山市湖南町を事例として
佐藤 優紀(武蔵大学大学院)
本研究では栃木県鹿沼市草久に鎮座する古峯神社にて、近年の古峰ヶ原講の数を把握し、その中から福島県郡山市湖南町を事例として古峰ヶ原講の実態に迫った。古峯神社では、祈祷と神札購入の申し込みをする際に、「御祈祷神符申込書」を記入する。平成十五年(二〇〇三)の講中向け「御祈祷神符申込書」によると、平成十五年(二〇〇三)の総講数は、のべ二九一二講である。県別講数は、講中が多い順に福島県八八一・山形県四四二・宮城県三七一・新潟県三二〇・岩手県二六五・埼玉県一五八・栃木県一五一・千葉県一四二・群馬県七〇・秋田県四〇・茨城県二七・東京都二四・神奈川県二二・山梨県一〇・長野県八・静岡県一となっている。ここから、東北地方の信仰が厚く、関東甲信越から青森県を除いた東北地方にかけて信仰圏が広がっていることがわかる。
さて、最も講中数の多い福島県から、郡山市湖南町を調査地として選出した。福島県郡山市湖南町は、郡山市の南西、猪苗代湖の南岸に位置する総面積一六七.七三平方キロメートルの町である。世帯総数一二八八戸、人口総数三九八九人(平成二十一年四月現在)であり、現在活動している古峰ヶ原講が一七講ある。解散した講を含めると、以前は二二講が組織されていたことになる。全ての講において、具体的な結成の理由や経緯、年代は伝わっていなかったが、古峯神社が火の神様であり、火伏せのために参拝しているという意識は強かった。殆どの講が、集落内に古峯神社の石塔を建立しており、それらの建立年代には講が組織されていたことが推測できる。講員は、基本的に地区の全戸が加入しているが、本村など家の密集した地区では抜ける家も多い。古峯神社への参拝形式は代参であり、抽選で選出する。クジの形は様々であるが、湖南町東側地域は紙コヨリを引く形が多く、西側地域では一升枡の中にクジを入れて振り出す形が多い。人数は講によって異なるが、二名から五名程度が選出され、古峯神社へ参拝し講員分の神札を拝受することとなる。拝受した神札は、地区に建立されている石塔に納めたり、各戸へ配布し神棚や火元である台所などに奉る。
湖南町では会津バス観光による古峯神社代参ツアーに参加する講が多い。ツアーは一月の寒くて積雪の多い時期に実施されるが、会津バス観光にて様々な手配をしてもらえることから安易に代参に行ける手段として活用されているようである。また、古峯神社代参ツアーでは、成田講をもターゲットにし、成田山への参拝も企画している。湖南町にも古峯神社へ代参する際、一緒に成田山へ参拝する講がある。これらの講では、古峰ヶ原講とは別に成田講も組織されていた可能性を検討した。
また、湖南町の西側地域では、別火講が行なわれている。別火とは日常の火ではなく、新たに点けた火によって儀礼などを行なうことである。別火講では、地元の愛宕神社の神主が祈祷し、愛宕神社の神札を拝受するのであるが、ある講では別火講と古峰ヶ原講が同一のものとして認識されている。これは、本来、愛宕信仰に付随する別火講に、同じ火の神である古峰ヶ原信仰が混同されていったのではないかと思われる。
最後に、代参に際の費用に関して考察した。各講では、代参の費用を様々な方法で徴収している。積立金や、代参前に講員からの徴収、自費で立て替え払いをし帰村後神札代を徴収する方法である。これらの方法は、講員が時代ごとに考えながら編み出した徴収方法だと思われる。代参の費用について次のような話が聞けた。「代参の費用に一戸一〇〇〇円ずつ集金していた。しかし、最初に代参に行く人は問題ないが、最後に行く人は物価の変化によって、自費で費用を補うことがあり良くないということになった。そのため、神札代は地区から金銭を出し、旅費は個人負担となった。」という。同様に、「物価によって代参費用の積立金を総会で話し合い変えている」という話や、「最初と最後の代参では、物価の上昇で最後の代参者が自費で補うことになり、それでは困るので、一度に代参に行く人数を増やした」という話も他の講から聞くことができた。各講で、徴収方法や金額を変更したり、代参者の人数を変更し短期間で講員全員が参拝に行けるようにしたりと、物価変動に対応していることがわかる。そこには「講員全員に不公平がないように」、「公平に代参にいけるように」、という思いがある。代参とは、講員の代表として神社に参拝にいくことであり、そこに偏った金銭の負担が生まれてしまっては、代参が続かなくなってしまうのである。
本研究では、湖南町における古峰ヶ原講の研究のみに留まったが、今後は他地域の古峰ヶ原信仰との比較研究を行なっていきたい。
情報化時代における墓と葬送の変化
坪内 俊行(慶應義塾大学大学院)
日本人は無宗教を標榜する人が多いとされ、宗教離れが進んでいるが、死者供養や先祖祭祀が消滅したとは言えない。親族が亡くなり、死後に何らかの儀礼や行事を行わない人はほとんどいない。葬送儀礼そして先祖祭祀にあたり、その重要な要素となっているのが墓である。お盆や彼岸は、墓参りがその中心となっている。日本には多様な墓のあり方があり、これまでも両墓制や無墓制などが民俗学では議論されてきた。しかし今日問題となっているのは納骨堂やヴァーチャル墓など新しい形態の墓、そして葬送の多様化に伴い誕生した墓石を持たない樹木葬や散骨など新しい埋葬法である。
日本には宗教法人格をもつ仏教寺院が約8万カ寺も存在し、その多くは境内墓地が併設されている。しかし、後継者不足が問題となり、個人墓を建立せず合同祭祀式の納骨堂を選択する人も多く、極端な場合には墓を建立せずに自宅で遺骨の供養を行う人もいる。葬式も身内だけの家族葬形式が増え、近年では火葬場で読経のみを行う直葬も一般化しつつある。このような状況において寺院や僧侶、そして墓はこれからも必要とされるのか。情報技術を駆使したヴァーチャル墓の誕生から約10年が経過しており、その実態を調査することで人々の墓や葬送に対する意識変化を考察する。
仏教寺院のヴァーチャル墓は、現実空間に遺骨を納めた墓もしくは納骨堂があり、利用者の心理的不安を和らげている。民間企業のヴァーチャル墓では、新規参入は容易であるが、実際の墓は寺院墓地や霊園にある場合が多く、信頼性や永続性に不安が残り、利用者の増加が進んでいない。また、利用料金は安価だが、事業撤退やサービス中止の危険性がある。個人が運営するヴァーチャル墓は、作成者の高度なシステム知識が必要なため建墓数はまだ少ない。しかし故人と関係ある人々が頻繁にホームページを訪れて思い出を語りあうなど、生者による様々なコミュニケーションが展開されている。
従来の墓は、遺族により祭祀される対象であり、継承者が消滅しない限り祭祀が約束されていた。今までは墓というものは変わらないからこそ、人々の崇拝の対象であった。しかし、情報化が進むと唯一の存在ではなくなり、誰もが複製可能な存在へと墓は姿を変えている。
ヴァーチャル墓は、企業による利潤を追求する新しいサービスとして提供されたが、単体での収益事業としては成立が困難であった。ただし、人々が失っていた宗教や寺院、墓への関心を呼び戻す契機になった。情報化の取組み策としてヴァーチャル墓が用いられた寺院では、ヴァーチャルな墓を選択しながらも、人々は実際に本堂で行われる供養法要へと足を運んでおり、寺院の活性化につながっている。
人は必ず死を迎える。そのため見えない世界に興味を持ち、死後の環境を意識する。ただし、死や他界を恐ろしいものと考え、見たくない気持ちも持ち合わせている。ヴァーチャル墓とは、見えない世界を可視化するひとつの手段である。
墓とは、死者を祭祀する死者のための施設だった。しかし死生観が変容し、墓は生者のものへと変化した。従来の墓との関わりは、隣接墓地へのお参りなどしない閉鎖的コミュニケーションだった。しかし情報化時代における墓との関わりは、複数化し解放的コミュニケーションへと変化している。見知らぬ他者からお参りされることで、新たな生者間コミュニケーションが生まれ、悲しみを癒し遺族に生きる活力を与えている。
石製の物体であるかつての墓は、経年により風化し、管理費の支払いが滞れば撤去され、無縁墓として合同祭祀されてきた。しかしインターネット上に建墓されたヴァーチャル墓は、システム上の要件さえ満たせば未来永劫にわたり残る可能性がある。継承者が絶えて無縁化が進んだヴァーチャル墓が今後発生しても、血縁による墓の安定システムが崩壊すれば、その処理をする担い手がいない現実が残されている。墓と葬送の自由を手に入れた代償として、将来に対する不安も生み出されている。
昔から人々は、見えない存在の力を感じ、興味関心を抱いてきた。日本おける死者の供養とは、魂の供養だったのである。その魂は仏壇や位牌そして墓に宿るとされ、人々に供養されてきた。しかし現代においては、それらの物体が魂の依代となることに疑問をもつようになり、新しい霊魂観が創出されている。情報化が進むにつれ、ヴァーチャル墓も徐々に認知され、お参りの対象へと変化している。手元に遺骨を置いて故人を偲びながら、ヴァーチャル墓をお参りする新しい供養方法も誕生している。実体のない墓については賛否あるが、人々の故人を思い偲ぶ気持ちは消滅していないのである。
ヴァーチャルな世界は不確実なものであり、インターネット空間におけるヴァーチャル墓は、今後も継続的な調査研究が必要である。
浦島伝承の研究
山田 栄克(國學院大學大学院)
浦島伝承とはなにか。動物報恩か異郷訪問か、時間の超越なのか、それとも見るなの禁か。日本には様々な浦島が存在しており、これらのモティーフを含まない「浦島」も数多く確認できる。例えば「丹後国風土記逸文」の「浦島」は動物報恩を含んでいない。
また、これらのモティーフを含むのは浦島伝承だけではない。例えば海幸山幸神話は異郷訪問のモティーフを持つ話である。そして、この海幸山幸神話は、異郷訪問という類似から浦島伝承との関連が指摘されてきた。このような部分的なモティーフの一致に基づく研究は、これまでの浦島伝承の研究の一主流であった。それは「浦島型説話」という表現に端的に表している。
しかし、それぞれのモティーフの研究が浦島伝承の研究であるとはいえない。なぜならモティーフは時代や地域によって大きく変化するからである。では、なにをもって浦島伝承とすべきか。それは、「浦島」という固有名詞であると考えられる。つまり浦島伝承の研究とは、「浦島」という固有名詞にこだわって行なわれるべきなのである。
本論文では浦島伝承の中でも、伝説を中心に浦島伝承とはなにかについて論じた。ちなみに、二〇〇〇年から二〇〇四年まで四回開催された「うらしま伝説交流サミット」の冊子によると、浦島伝説の伝承地は、二四ヶ所あまりあるとされている(うらしま伝説交流サミット『第四回うらしま伝説交流サミット記録集』 二〇〇四年 うらしま伝説交流サミット)。
本論文で論じた浦島伝承は、遠い存在ではない。なぜなら私たちが生活している様々な場面で「浦島」と出会うことができるからである。例えば、久しぶりに故郷に帰ってきた時に故郷の変貌ぶりに驚き、「浦島太郎のような気持ちだ」と言っても会話は成り立つ。この文言が成立するのは、発話者と聞き手が互いに浦島の話を知っているためである。こうした「浦島」という知識は、国定教科書に採用されたことを契機として、日本全国に画一的な内容の話が広がることによって刷り込まれたものである。そして、こうした「浦島」という知識の広がりは、様々な伝承にも変化を与えている。
その例として岐阜県中津川市山口地区を挙げることができる。この山口地区には、乙姫岩(龍宮岩)といわれる岩があり、ここに浦島が流されてきたという話が村誌などの文献によって確認できる。確かに、実際に訪れて聞くと、乙姫岩(龍宮岩)という呼称は伝承されてきたことが確認できた。しかし、浦島伝承に関しては確認できなかった。この山口地区の浦島の話は、一九七二年に当時の隣町の広報誌に掲載された記事が大きな転機となっているようだ。調査の限りにおいて、山口地区の浦島の話は周辺住民に知られていなかったが、広報誌や案内板の設置、そして「浦島」「乙姫」といった交差点の命名などの行政の働きかけが一九七〇年以降、盛んに行なわれた。それに加え、乙姫岩(龍宮岩)の存在や、海に関する屋号などもあいまって、周辺住民も徐々に、地元の話として浦島の話を受け入れ始めている。
こうした他の伝承と重ねられ、新たな伝承や事物が作りあげられていくというのは、この山口地区のみではない。京都府京丹後市網野町に関わる近世文献においては、動物報恩や亀にまたがって異界に行くというモティーフは確認できない。それにも関わらず、網野町にある浦島を祭神とする島子神社には、一九四七年に奉納された「龍宮亀」という亀の石像に乗るように、一九九九年に「浦嶋太郎像」が奉納された。また、同じく浦島を祭神とする網野神社でも、腰蓑をつけた浦島が玉手箱と釣竿を持ち亀にまたがっている絵馬が近年、用いられるようになった。これは図像に限ったことではない。周辺住民は浦島が実在の人物として認識しながらも、その人物像は「助けた亀に連れられて」龍宮に行く浦島である。それは浦島を祖先とする氏族伝承を持ち、家系図を所持する家でも同様である。
このように、浦島伝説の伝承地を訪ねてみると、伝承者は自らの土地の浦島の話と、「助けた亀につれられて」龍宮へ行った浦島の話を知っていることに気がつく。さらに地域によっては他の伝承地の浦島の話をも知っていることがある。これは、過去にその土地に実在した人物としての浦島の話、昔話のようなフィクションとしての浦島の話。この相反する性質の二つの話は、どちらかを否定するのではなく、「浦島」という固有名詞の一致から同一視され、伝説として成長・変化しているということである。また、時に伝説と関係なかった地名を結びつけて「浦島」を「発見」したり、時に新たに「浦島」にかかわる事物を作り上げたりしているのである。
こうしたことから浦島伝承とは、昔話と伝説が交錯し、そして成長・変化している伝承であるといえる。
現代における昔話と「語り」の機能―ストーリーテリングを事例として―
斎藤 みほ(首都大学東京大学院)
今日の日本において、昔話の語りは人々の生活の中から姿を消し、昔話を含む民間説話は終焉したといわれている。現在みられる昔話の多くは、本に書かれた形で、主に子どもを対象として広まっている。昔話が本来、人々の生活の中で口から口へと伝承されるものであることを前提とすれば、確かに現代の生活の中に「生きた」昔話を見ることはほとんどないといえるだろう。しかし一方、新たな機会・場において、語られる昔話があることもまた事実である。
本発表で取り上げる修士論文では、現代社会における昔話の「語り」に注目し、現代の語り手と称される人々の実践と活動について調査・分析を行った。この現代の語り手とは、本から昔話を覚え、主に図書館や小学校などの場において子どもを対象に語りを行う人々を指す。彼、彼女たちは「都市の語り手」と称され、その語りの活動はストーリーテリングと呼ばれている。ここでは、この「都市の語り手」が「語り」を作り出す過程を参与観察したデータに基づき、これまで民俗学で主に研究されてきた「伝承の語り手」のものと比較し、それぞれの記憶形成方法における相違や伝承形態の相違を示した。また、「都市の語り手」が生まれてきた時代背景と、そこで生じる昔話の変化の問題を取り上げながら、現代における語りの意義を考察する。
「都市の語り手」が、それまでの口承によって昔話を伝えてきた「伝承の語り手」と大きく違う点は、文字の介在であり、昔話を本から覚える点である。「伝承の語り手」が声による伝承の上に成立してきたのに比べ、「都市の語り手」は文字から昔話を覚えるため、口承文芸とは異質のものであるといえる。しかし、「都市の語り手」が文字言語から「語り」を作り上げ、音声言語へ変換する過程を分析することによって、「伝承の語り手」が口承のなかで無意識に身につけてきた「語り」という行為を再考察・再分析することが可能となった。ここでは主にW.J.オングの唱えた「声の文化」と「文字の文化」の比較から、音声による記憶形成と文字による記憶形成の相違を明らかにし、物語を暗唱することと語ることの違いを示した上で、「都市の語り手」の課題とされる点を提示する。
また、「伝承の語り手」と「都市の語り手」の社会的役割と意義の比較を次のように行った。まず、「伝承の語り手」による昔話は、古来の民俗的感情や村落社会を維持する一つの倫理を伝えてきたと考えられてきた。そのため、柳田國男は昔話から日本の固有信仰を究明しようと試みた。また、関敬吾は、語り手と聞き手との集団を「物語共同体」と呼び、昔話は村落社会を基盤とした共同体に所有され、また共同体を結びつける機能を持つと考えていた。つまり、「伝承の語り手」によって伝えられてきた昔話は、村落社会の人々を通時的な縦のつながりと、共時的な横のつながりで結びつける役割を果たしていたと考えられるのである。
その一方で、近代日本における児童文学と印刷術の発展に伴い、昔話は子ども向けの読む物語として変貌を遂げる。文字化された昔話は、村落共同体の文芸から大衆社会の文芸へと大きく移行し、書籍によって広く一般に広められることとなった。同時に一部の昔話が子ども向けに童話化され、その内容を大きく変更されるという問題も指摘されてきた。
さらに、昔話の伝承形態は高度経済成長期のなかで、村落共同体の崩壊と共に大きく変化し、「伝承の語り手」は消失することとなった。昔話は何世代にも亘って繰り返し語られることで、人々を過去とつなぐ役割を果たしていたといえる。しかし、高度経済成長という大きな時代の変化のなかで“世代の断絶”が生じ、昔話はその通時的なつながりを見失うこととなったのである。また同時に民俗学はその研究対象を失い、昔話は終焉したとも考えられてきた。しかし、その一方で、文字化・童話化された昔話は書籍として残り、その後、現代社会のなかで生まれた、子どもを核とした母親同士のコミュニティにおいて語られるようになった。そして、そこでの「語り」は、共時的な横のつながりを生み出す働きをするようになる。
現代のストーリーテリングは、“語りの場”を作ることによって、語り手と聞き手の交流を生み出し、その場における共時的な横のつながりを得つつある。その中で、語られる昔話は、語り手と聞き手に共有され、肉声の言葉にされることで、再び「生きる」道を見出していると考えられる。また、ストーリーテリングは、現代の語り手たちの視点からみると、語り手たちにとっての生きがいや、彼女たちが地域社会に参加する主体性とアイデンティティを得る手段としての意義を持っているということが、「都市の語り手」たちの調査から明らかになった。
インターネットにおける「語り」と「物語」の生成
池松 瑠美(東京大学大学院)
パソコンや携帯電話等の電子機器の普及と共に、インターネットの利用者は近年、増大しつづけている。それに伴い、メールのやりとりや電子掲示板の利用等、インターネットを介したコミュニケーションも増加している。インターネットには閲覧者に向けた様々な語りが見られるが、中には単なる出来事の羅列や情報の断片の交換ではなく、複数の出来事を結び付け、意味づけを与える、プロットを有する物語も多く見られる。また、ブログに見られる自分の日常についての語りのように、インターネットは個々人による語りの場として機能すると同時に、近年では、電子掲示板上の複数の投稿者による書き込みが一つの物語として受けとめられ、書籍化・映像化される等、時には複数の投稿者の語りによって物語が形成されていく場ともなっている。修士論文においては、インターネットにおいて、プロットを有する物語が生成する過程を考察するため、「世間話」をコミュニケーションとして捉え直すと同時に、人から人へと語り継がれることで、つまりはコミュニケーションを介して物語が生成することを論じた。
その上で、修士論文では具体的な事例として、2つの「都市伝説」、「鮫島事件」と「杉沢村伝説」を取り上げ、それぞれの「都市伝説」がインターネットやその他のメディアを介してどのように広まっていったのかについて考察を行った。本発表においては、電子掲示板「2ちゃんねる」を中心に広まった「鮫島事件」を取り上げ、架空の事件とされるこの「鮫島事件」がインターネット上でどのように広がっていったのかを書き込みに実際に登場する「柏」と「EOM」という2つのキーワードに着目して論じた。
架空の事件であり、「ネタ」であるとされるこの「鮫島事件」は、2001年に「2ちゃんねる」に立てられた「伝説の「鮫島スレ」について語ろう」というスレッドへの投稿が、その発端であったとされている。当初行われた複数の書き込みが自作自演であった可能性も指摘されているが、その後「2ちゃんねる」内には関連したスレッドが複数立てられており、さらに、「2ちゃんねる」外部にもこの事件について触れたサイトが複数存在する等、「鮫島事件」はインターネット上で拡大していったことが窺える。また、前述のスレッドが立てられてから10年近く経った現在でも、インターネット上でこの「鮫島事件」が話題として取り上げられることがあり、インターネット上には「鮫島」という島に関する物語や、「鮫島」というハンドルネームを使用していた人物についての物語等、この事件にまつわる複数の物語を見出すことができる。
事件について語ることがタブーであるとされている「鮫島事件」が拡大するその過程を見てみると、当初書き込まれた非常に断片的な情報に対し、実在の地名である「柏」のように、細部を付け加えるような書き込みが重ねられ、プロットを有する物語が生成するケースが見られる一方で、本発表において取り上げたもう一つのキーワード「EOM」のように、断片的な情報の提示にとどまるケースも見受けられた。この「EOM」は、インターネット上でよく使われる言葉「ROM」の打ち間違えであるという書き込みも見られるものの、何を意味する言葉なのか具体像の提示がないまま、断片的な情報を提示するのみの短い書き込みが繰り返されている。
この「EOM」のように断片的な情報の提示に留まる書き込みが続けられる背景を理解するためには、インターネットの語りの特徴についても考察する必要が出てくる。そのため、本発表では、インターネットの語りが文字による語りとしての特徴(字体の変化や改行といった文字による視覚的効果を狙った語りが見られる、長く複雑なプロットを持った物語が見られる等)が見られる一方で、即時性や書き手と読み手の流動的かつ双方向的な関係といった口承の語りに共通するような特徴を有していること、さらには、画像や動画、他サイトへのリンクを取り込んだ語りが見られることに言及した。その上で、不特定多数の人々が閲覧・参加することが可能である電子掲示板のようなインターネットにおいては、投稿者の間で互いのリテラシーを確認しあうようなコミュニケーションが見られることに触れ、「鮫島事件」で見られた暗黙のルールにのっとりタブーであることを強調する語りが繰り返されるケースや、前述の「EOM」のように断片的な情報の提示のみが繰り返されるといったケースは、こうした投稿者同士のリテラシー確認の意味を持つ可能性があることを論じた。