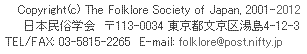HOME > 談話会開催記録 > 2010年 > 第849回 > A会場|B会場
談話会要旨-第849回(2009年度 民俗学関係修士論文発表会)A会場
一升仁義考―葬儀からみる兄弟分慣行の特徴―
泉田 慧(筑波大学大学院)
本論文は愛媛県今治市大三島町において行われているキョーダイツキアイという慣行について、民俗学研究の立場から、特に葬儀の場におけるその特徴を分析・考察するものである。
このキョーダイツキアイは、民俗学においていわゆる親友系兄弟分慣行と呼ばれるものである。しかしながらこの親友系兄弟分慣行についての民俗学的立場からの研究は、1969年に竹田旦によって発表された論文、「兄弟分の民俗について」〔竹田旦 1969年4月「兄弟分の民俗について」『日本民俗社会史研究』 pp165-214〕以来、特に発展することがないまま今日に至っている。筆者はその理由を考察するとともに、竹田の行った研究に対して批判を行った。結果として、次の3つの問題点があることを指摘した。1点目、分析を行うにあたって取り上げている事例の情報が断片的であり、推測によって分類されていると考えられる部分が多い、かつ、分類の基準が曖昧であること。2点目、「兄弟分」、あるいは「兄弟のよう/以上」という呼称、表現に拘り、実態をみていないこと。3点目、兄弟分という慣行のみに注目しており、他の社会集団と比較してどのような特徴があるか、という点がみえてこないこと。
以上の結論から、今後明らかにすべき課題として①他の社会集団と親友系兄弟分との関係。②親友系兄弟分として行われる交際の内容と持続性。③兄弟分慣行形成の契機即ち、親友と親友系兄弟分の差。という3点を提示した。
さらにこの3点の課題を明らかにするための調査の場として、一升仁義という葬儀の交際を切り口とすることを選択した。その理由は以下の通りである。まず、香典帳を用いることで、調査対象者の持つ人間関係を広く捉えることができるため。次に葬儀に関わる他の社会集団と親友系兄弟分との比較を行うことが可能となるため。最後に聞き書きと香典帳を併用することで語りにおける表現と実態の差を捉えることができるため、である。
なお、一升仁義という交際の担い手としては、「キョーダイ」と呼称される親友系兄弟分の他に、個人の所属する家と、その家からの婚出者と婚出先、家への婚入者とその生家を中心とした人間関係を意味する「シンセキ」、「向こう三軒両隣」に居住する住民である「キンジョ」などが挙げられる。
調査を行った結果、当地の親友系兄弟分には次のような特徴があることが判明した。①他の社会集団と比較してどのような存在か、という点については、互いの合意によって形成される1対1の関係であり、ただいい交わすのみで成立すること。相手を選択する際には同性で同じ集落内に居住している人物が選ばれること。キョーダイ関係を構成するか否かは個人の意思に任されること。交際の期間が比較的短い、ということ。以上である。②親友系兄弟分として行われる交際の内容と持続性という点については、一升仁義となる、という以外、絶対に行うべき交際という規範は存在しないこと。親友系兄弟分としてどのような交際を行うかは人によって異なる、ということ。交際を行う期間は親友系兄弟分となった者同士と、その配偶者が亡くなるまで、と限定されていること。以上である。最後に、③兄弟分慣行形成の契機、即ち親友と親友系兄弟分との差については、通常他人は排除されるような儀礼の場にも参加が許されること。個人的欲求を充足することが親友系兄弟分には求められるのではないか、と考えられること。以上である。
またこれらの結果から、調査地においていわれる「兄弟のよう/以上に」つきあう、世話をする、という言葉は、単に親密さを表現するものであって、具体的な交際内容や持続性が血縁兄弟と同等、それ以上につきあう、ということを意味していない、ということが指摘できた。よって、従来これらの言葉を即実態と捉えてきたことには、やはり問題があるのではないかと考えられる。
本稿では葬儀の場を通じて親友系兄弟分慣行について調査を行うことで、語りのみに頼らずに交際の実態に迫ることができた。その結果としてこれまで行われてこなかった、兄弟分の交際の持続性、血縁兄弟との比較、兄弟分と友達との相異について明確に示したことは、大きな成果ではないかと考えられる。
村の嫁として生きることの位相 -女講中をめぐる嫁の価値判断―
齋藤 優美(筑波大学大学院)
嫁入婚において、女性は家における属性が実家の娘から婚家の嫁へと変わるが、更に村外婚であれば、外来者として嫁ぎ先社会に受容される手続が必要になる。それは女性中心の宴への参加だったり、女性の講集団へ加入だったりと様々だが、一方的に認められるだけでなく、嫁自身が新しい関係性を築いていく契機ともなる。
村落における外来者受容を説明する概念として、鈴木栄太郎が整理した「村入り」がある。鈴木の分類を基礎とし、「一軒前」の家の成立との関連において研究は展開された。このため、「村入り」の対象は戸主や婿に限られたが、「村入り」研究の萌芽期(1934年「山村調査」)には、戸主の妻が女性の祝宴に参加することで「村入り」を果たす例、すなわち家ではなく個としての外来者の視点が挙げられていた。嫁個人の社会加入に関連する近年の論考として、村落におけるフォーマルな関係=男性集団、インフォーマルな関係=女性集団いう二つの社会関係を抽出した服部誠の『婚礼披露における女客の優位』がある。ただし、集団と社会は必ずしも同義ではなく、複数女性集団が存在していたり、また集団に属しない嫁等を存在することもありうる。様々な要素との関連に留意し、単純な変遷ではなく、立体的・重層的に村落の女性社会を捉えることが重要である。この作業を位相と呼び、本稿は、集団への仲間入りという観点ではなく、女性社会という枠組みで、村落における嫁の生き方を捉えることを目的とする。
本稿では、宮城県牡鹿半島(大原浜、給分浜、小渕)における嫁集団および嫁個人について論じる。牡鹿半島については、男性による村落組織・契約講に見る社会構造分析が、竹内利美や平山和彦らによって行われたが、女性集団については補足事例として扱われるにすぎなかった。しかし、牡鹿半島の各村落に分布する嫁集団・女講中は、女性社会の核としての意義を担い、男性を含めた村落社会全体に対しても還元・干渉する力を持っていた。例えば、婚礼時に女講中が担った、嫁入道具の引渡し儀礼「長持渡し」は、全国的には男性特に若者の役割として分布している。平山和彦は若者集団が婚姻に関与しない理由を家父長権に求めたが、女講中が未婚女性を仲間と見なし男性社会の補完的役割を果たしたと考えることもできる。また、長持渡しは嫁を村落から送り出すときと迎えるときで作法に違いがあり、報酬の額に大きな違いが出る。長持渡しは、女講中が村落の女性社会を表象して仲間の受容・排除を行う儀礼的意味だけではなく、女講中の収入源のとしてきわめて重要といえる。この収入により、女講中は婚礼道具・飲食器を揃えていたが、女性だけではなく、男性の会合や学校・役所にも要請があれば貸し出していた。このほか、産婆への謝礼や講員への見舞金など、講員への福利厚生的機能も有していた。
観音講など上位の女性集団に比べ、女講中は実利的意義や社会的影響が大きかったといえるが、この集団が村落の嫁全てと同義だったわけではない。例えば、漁村集落である小渕では、家督以外の男性に嫁いだ女性は女講中に入れない一方で、加入を勧められればそれを拒否する権限が嫁自身にはなかったため、女講中により嫁が完全に二分化していた。しかし同時期、在町的性格の強い大原浜では、基本的に全ての嫁が加入することができるが、姑の意思により加入できないケースが現れ、女講中への加入は社会構造ではなく家ごとの任意的なものになっていた。昭和40年代に入ると、結婚後も仕事を続ける女性が増え、それを理由に加入を断る傾向があらわれるようになり、小渕等周辺村落にも波及していくようになる。女講中衰退の背景には、長持渡しによる経済システムの不振、集団としての魅力の減少などとともに、更に家および個人の意思に重きを置く形に変化していったことがあげられる。
昭和50年代以降、村落における女性社会の中心は婦人会へ移行していったが、婦人会は臨時・緊急時の集合という性格が強く、女講中の代替組織とはならなかった。この頃より表れ始めたのが、外国出身の嫁たちである(以下、外国人嫁)。調査地における外国人嫁の国籍はフィリピン、中国、韓国、台湾と多様であり、結婚の経緯や日本語の習得度もそれぞれに異なる。同国出身者が近隣に在住している場合、彼女たちは密なネットワークを形成し、それを頼りにする。他方、村落の側でも同国出身者が複数いる場合、外国人嫁の属性のうち国籍を意識し、外国人嫁同士に全く付き合いがない場合でもグルーピングしてしまう傾向がある。こうした状況の原因として、村落における女性社会の連帯がうまく機能していないことが挙げられるが、その影響は日本人より外国人の嫁にとって大きいといえる。外国人嫁については、地域社会における女性集団の発達という枠組において、今後の研究課題とする。
洪水対応をめぐる生活知の民俗学的研究―利根川下流域の近世新田村を事例として―
金子 祥之(早稲田大学大学院)
第一章:本研究の立場
本論の目的は、いわゆる洪水常襲地と呼ばれる地域に住む人びとの洪水対応の生活の知恵を明らかにしていくことである。
なぜこのような立場をとるかといえば、こんにちの洪水対策における主要な二つの立場、すなわちハード論とソフト論が、地元の人びとにとってどちらも外部からもたらされるものであることと関連する。つまり、洪水対策が行政に一元化され、防災対策は高度に専門分化されたものになっているのである。
けれども、このように行政に一元化された対策がかえって災害の被害を大きくしているという指摘がある。そのため、こうした一元的・専門的な災害対策への反省として、災害対応における生活知の有用性や、日常的な関係性を基盤にした災害対応の重要性が指摘しされている。こうした研究群に依拠すれば、地元住民の生活の立場から、災害対応を考える必要性があると考えられよう。
そこで、本論では二つの事例研究をおこなった。
第二章:被災体験の物語りと洪水対応の生活知
研究事例のひとつめは利根町を対象としたもので、「ミズが分からなくなった」という、地元の人びとの表明に注目した。そして、地元の人びとを洪水の危険から守るためのハード設備が整えられていっているにもかかわらず、何ゆえに地元の人びとは不安を抱いているのかを明らかにした。その不安感は、昭和五十六年の洪水を通じて感じられたものであり、人びとが災害を体験するなかで、深められてきた生活知と実際の洪水とのズレに起因するものであった。
地域の人びとが、蓄積してきた生活知には、説明的な性質と教訓的な性質という異なる二つの性格があった。
こうした二つの性質のうち、ハード設備が充実していくことが環境条件の変化をもたらし、生活に身近なものと引き付けて洪水の性質がどのようなものであるかを説明する説明的な生活知の妥当性が揺らいでいった。
すると、それをもとにしながら、蓄積されてきた教訓的な性質のもつ有効さも鈍ってしまう。こうして、これまで有用であった二つの経験知が覆されたのであった。
まとめると、近代治水は洪水を差し迫ったものではなくしたといえる。けれども、経験知の有用性を鈍らせたことで、どのような被害がくるのかが全く想像もつかないものにしてしまった。したがって、洪水に対しては具体的な対処の仕方がわからなくなってしまったのである。このことこそが、人びとが不安を抱いた理由なのである。
第三章:水神祭祀による洪水対応とその継続の意味
つづく三章では、千葉県栄町の布鎌地域に伝承されている布鎌惣社水神社の秋季大祭を取り上げた。ここで、理解を試みたことは次の二点である。
ひとつは、水神を媒介とした洪水対応のありようを記述するということである。とりわけ、空間論的な視点から、祭礼全体を記述することで次のような結果が得られた。すなわち①布鎌地域では、水防上重要な先端部分に二つの水神社を配することで、土木的にだけでなく、心意的にも洪水に対処してきたこと。さらに継承されてきた二つの神事(神輿の渡御還御と奉納相撲)には水防祈願という共通性があることが明らかになった。それは具体的には、②神輿の渡御還御の儀礼は、集落全体を守る堤防の合流点に水神の神霊をこめるという意味で執行される神事であること。③もう一つの神事である奉納相撲は、やはり堤の合流点で、人びとが土をふみしめることによって、堤の基礎をかため堤防の決壊を避けようという意味付けで行われてきたこと。
もうひとつの点は、洪水が遠のいていくなかで積極的な意味合いの薄くなってきた水神祭祀が、継続される意味についての考察である。水神祭祀が継続されるのは、川との間で緊張感を持ち続けていこうすることと関連がある。というのも、そこに住む人びとにとって、洪水はなくなったものではない。いつか来るものなのである。したがって、心意的環境対応である水神社の祭礼は「洪水の記憶」を喚起するという意味をもち、祭祀を通じて川とのかかわりを継続できるという点において、洪水が失われて久しい現在でも意味を持ち続けているのである。
終章:洪水対応における生活知の意味
洪水の被害を被る地元の人びとは、洪水を生活の文脈にひき込むことによって、既知のものとし、対応することができていた。すなわち、“災害を生活に内在化させる”ことが、洪水とかかわるという防災では肝要なのであった。
今日の災害対策は、それを徹底させていくなかで、未知の災害だけではなくて既知の災害までをも排除していってしまったといえる。けれども、住民自身が対応できるか考えると、災害を既知のものとしてきた人びとがもつ“災害を生活に内在化させる”ことのできる生活の知恵をこそ、大切にしなければならないと考えられるのである。
開発の民俗学に関する研究―朝日連峰の開発と山の民俗の変容-
石川 徹也(成城大大学院)
ダムや山岳道路などの開発による山の自然破壊の問題は、高度経済成長期ごろから「自然保護問題」として一般化するようになった。筆者は、そうした開発による自然破壊の現場を歩き各地に取材してきたが、その視点は当初は、山の生態系の破壊に向けられてきた。しかし、調べていくにつれて、巨大開発はその地域の生態系ばかりか、人間の生活そのものを破壊し、中でも伝承され蓄積されてきた民俗の衰退・消滅は、取り返しのつかないものであるということを感じるようになった。本稿の焦点は、開発によって、何が「取り返しのつかないもの」になるのかということである。
われわれの住む日本列島は山によって成り立つ「山島」である。大地の大部分は、山岳地帯によって占められている。我々は、山に関わらずには生きていくことはできない。なぜならば、水や空気をはじめ、われわれが生きていくうえで必要とされるもののほとんどが山で生まれているからである。われわれは、山に物理的に依存してきた本能を持つ。そうした本能が、山への親しみと同時に畏敬の念を育んできた。
山の神を信仰する民俗は、山に対する畏敬の念が表出したものである。そうした山に向かう敬虔な気持ちが日本人の精神を形成する大きな要素になってきたことは否定できまい。平野の農耕民にとって、山は祖霊が帰る地であり、山に住む人にとっては、山は自分たちの生業を支配する神がいる地と考えた。また、平野の人間からみると、山は自分たちの生きる世界とは異なる世界、つまり「山中異界」を形成する場であった。山中異界は、祖霊たちの住む楽園であると考える一方で、自然災害などをもたらす鬼の住む場でもあると恐れられた。
実際、狼や熊などの大型哺乳類が生息する地は、その厳しい地形もあってそうやすやすとは人間に都合のいいように開発のできない聖域でもあったのである。しかし、日本に住む人間たちは、この異界に挑み続けてきた。
現在よりも温暖化していた縄文時代中期には、八ヶ岳をはじめとした高所山岳地帯にも定住の痕跡が見られる。以来、山地は、鉱山や新田など、時の権力者による開発行為によって、その人口を増減させてきた。一方で、戦後の国際化は、山地の資源を必要としなくなる時代でもあった。鉱山や薪炭の必要性の減退は、山の人口を平地の工業地帯へと移動させることとなった。
そうした山の開発の中でも、山村の主要部を衰退させ、過疎化の進行に拍車を掛け、そして、山の民俗に重大な影響をもたらしたのが、ダム建設をはじめとした開発である。奥地から河口までの流域が一体となって生活圏を築いてきた日本の河川において、その流域圏を寸断するダム開発は、その生活圏に致命的な亀裂を生じさせてきた。そうした弊害は、まずはダム予定地での山村の衰退・消滅によって、山に住む人間が減少することで、その地域の山の民俗を喪失させたばかりか、水源地である森林も手入れがなされずに荒廃の度を深めている。
山の民俗の喪失は、この列島の特徴でもあった多様な文化が、単一化された文化へと単純化されていく危険性を孕んでいる。現在は、そうした喪失のデッドラインに位置している。山における開発の歴史を振り返り、その過程で失われた、または失われつつある山の民俗の価値を凝視することは、混迷を深めるわれわれの社会の今後のあり方を考えることでもある。
筆者は、そうした開発による民俗への影響を検証する学問を「開発の民俗学」と定義し、山岳地域ごとの検証を試みようと考えた。修士論文においては、まず「開発の民俗学」は、開発による民俗への影響を考察する学問を目指すものであるが、どのような方向性を持ち、どのような民俗が考察対象となるのかなどについて、筆者の考えをまとめた。
考察対象としての山の民俗は、東日本・中部地方に多いブナ帯と西日本に多い照葉樹林帯に分けられる。修士論文の考察対象としては、南東北地方の日本海側、山形・新潟両県境をなす朝日連峰西麓の三面集落(新潟県岩船郡朝日村)を選んだ。熊猟をはじめ、かつてブナ帯の民俗を色濃く残していた集落を対象に、ダムを主とした大規模な開発とそれに伴う山の民俗の変容を、断続的ながら十数年にわたるフィールドワークから考察した。また、山の民俗に対する開発行為に対する抑制の民俗として、「開発規制の民俗思想」や山中異界などについて、筆者の知識の及ぶ範囲内での考察を試みた。
ブルターニュの「神」と「悪魔」―フランス民俗学者セビヨの視点から―
鈴木 文子(東北大学大学院)
ポール・セビヨ(Paul Sébillot, 1843-1918)は、フランスを代表する民俗学者の一人である。日本民俗学の祖である柳田國男はセビヨをフランス民俗学の創始者としてみなし、「口承文芸」という語をセビヨの “la littérature orale” から取り入れた。フランスにおいても、セビヨはフランス民俗学の先駆者として位置づけられている。しかしながら、彼は今日において日本やフランスの研究者の間であまり評価されていない。その理由は、次の二点に集約される。すなわち、セビヨが自身の価値観を基準として、彼のインフォーマントである農民や漁師に接していたこと、さらに収集した資料を学問的に分類することなく、異質な要素の事例をただ羅列してしまっていることである。このような理由により、研究者はセビヨが収集した民間伝承に言及することはあっても、セビヨ自身を研究対象として扱うことはほとんどなかった。本発表は、これまで言及されることのなかったセビヨの民間伝承に対する分析的枠組みに注目することを狙いとしている。
セビヨは、自身がフィールドの対象としたフランスのブルターニュの民間伝承は、フランスの他の地域と比べて、非常に珍しい特徴を有していると主張する。すなわち、自然界においては、神によって創られた作品(神の作品、les œuvres de Dieu)と悪魔によって創られた作品(悪魔の作品、les œuvres du diable)とに二分されるという点がその根底に見いだされるのである。彼はこのような創造のあり方を「二元論的創造」(la création dualiste)と呼んでいる。また、セビヨの記述から「二元論的創造」とは、神の作品に対する、悪魔の対抗意識であることが理解できる。さらに、セビヨは両作品の性質についても記述している。それによると、神の作品は上等で有用なものである一方、悪魔の作品は下等で有害である。すなわち、セビヨは「二元論的創造」において、神の対極に悪魔を位置づけている。
しかしながら、セビヨの収集した民間伝承においては、先述した神の作品および悪魔の作品の特性が当てはまらない事例も記述されている。つまり、ブルターニュの民間伝承のなかには、「神」と「悪魔」による「二元論的創造」によって理解することのできる民間伝承ばかりではなく、「二元論的創造」によって理解することのできない民間伝承もあるのである。このことはセビヨのキリスト教についての考えと関係している。彼によれば、「神」や「悪魔」に関する創造物の「起源」はキリスト教による「創造」(la création)の考え方によって書き換えられたという。セビヨは、ブルターニュにおいては、キリスト教の布教以前に独自の信仰や慣習が存在したと考えていた。彼はそうした信仰や慣習を、キリスト教と対置させながら「異教」(le paganisme)と呼んでいる。
こうしたセビヨの「二元論的創造」の創出をめぐる背景を理解するとき、「二元論的創造」に関わる民間伝承と「二元論的創造」に関わらない民間伝承との関係性を理解する新たな視点を見いだすことができる。すなわち、キリスト教的な創造観によって形成されたものは、「神」と「悪魔」によるそれぞれの作品として記述されるのに対し、「二元論的創造」に関わらない民間伝承には、対極的な関係性にあるというキリスト教的な「神」と「悪魔」の関係性はそぐわない。このように、ブルターニュにおける民間伝承の諸事例は、必ずしも「二元論的創造」によって理解することができない。つまり、キリスト教的な創造観や、キリスト教的な「神」と「悪魔」の関係性では理解することができない。セビヨはそれらの事例を「二元論的創造」という視点で分類し、羅列した。しかしながら、セビヨの「異教」に対する視点を考察するとき、彼はキリスト教布教以前の「異教」を過去のものとしては捉えていなかった。彼はそれがキリスト教の影響を受けつつも、ブルターニュで存続していると考えていた。
柳田國男もまた、仏教などの外来の要素と、外来の要素からの影響を受ける以前より存続している「固有信仰」という視点を有していた。この点において、柳田とセビヨの直接的な影響関係を見いだすことはできないが、両者が同様の考え方を有していたことは特筆すべき点であろう。セビヨに関してはキリスト教布教以前の「異教」に、キリスト教化された伝承と同等の価値を与えていたとは言えない。ブルターニュに見られる民間伝承についてのセビヨの記述や彼の宗教的背景、政治的背景についての考察を通して、セビヨが指すブルターニュの「異教」と「キリスト教」を理解することができるであろう。