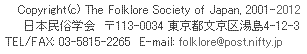HOME > 談話会開催記録 > 2010年 > 第850回
談話会要旨-第850回(日本民俗学会第62回年会in宮城プレシンポジウム)
歴史認識の学としての民俗学と変化
神奈川大学教授 福田 アジオ
生活は学問が存在せずとも続けられ、変化していく。民俗学が研究対象とする民俗事象それ自体が自ら民俗事象というラベルを貼って存在するわけではない。民俗学という学問が成立する過程で、生活の特定の事象が民俗として認識され、把握されるようになったと言える。従って民俗は民俗学という学問研究とともに存在する。
民俗学を意味し、民俗事象をも意味するFolkloreは、1846年にトムズによって作り出された単語である。19世紀の民俗学が、社会から切り取った事象は、それが体験の時間を超えて遥かな昔を教えてくれる存在と認識したからであった。そして、現在の事象のなかから起源を明らかにしようとした。
20世紀民俗学は、それを克服して、変遷過程を把握する学問となった。日本の民俗学を切り拓いた柳田国男は、1908年の二つの体験から、この学問内容を自ら発見し、二つの著作を著した。歴史は直立ではなく、平野から山間地へ向けて立てかけた棒という認識が後に民俗学に発展した。欧米民俗学の影響を受けて日本の民俗学は成立したと理解されているが、1908年にロンドンでゴムの『歴史科学としての民俗学』が刊行されたことを知れば、むしろ同時代的成立に注目すべきであろう。それが20世紀民俗学であり、起源論から脱した、変化・変遷論の、ゴムの言う、歴史科学としての民俗学である。
変化は二つの問題として論じられなければならない。一つは、研究成果としての変化である。もう一つは、研究対象としての変化である。この二つを統合して、過去から現在、そして形成過程を含んだ歴史像を形成する研究が21世紀民俗学と言える。
変化と変異―そして民俗はなぜ分布するのか―
前筑波大学教授 真野 俊和
民俗学研究の現場において私たちが最初に捉えることができるのは、一般に民俗の「変異」であって「変化」ではない。しかし私たちは多くの場合、それを変化の結果としての変異であると理解しようとしてきた。たしかに変化と無関係な変異形の発生は理論的にありえても、実際に適用可能なのはごく限られた対象だろうから、その発想に正当性がないわけではない。
ところで私たちが個々の民俗事象を変異形のなかの一つとして見るということは、同時に一定の民俗範疇の承認を意味している。そして同類の民俗は異なった土地に存在することによって分布を形成する。しかしそれらは大きな広がりのなかに飛び飛びに分散することもあれば、限られた広がりのなかに集中していることもある。マクロな視点において、私たちは「民俗が分布する」という事態を自明の概念として受け止めるのが普通だが、ミクロな視点から、すなわちなぜそれらは飛び飛びに、あるいはかたまって分布するのかということを考えはじめると、そう簡単に解けそうもない難問であることに、すぐに気づくであろう。なぜなら前者において、遠くの人々はどうしてそれを選び、近くの人々はどうしてそれと異なるものを選んだのか。いっぽう後者においてならば、隣の村の民俗を自分たちも採用しなければならない積極的な理由を考えにくいからである。
この難問ははたして解答可能なのか。私は今回の場を借りて、「変異」と「変化」、そして民俗の「分布」という事柄に関する根源的な議論の第一歩を踏み出してみたい。
日本民俗学の基本は、伝承論であり変遷論である
國學院大學教授 新谷 尚紀
柳田國男が創始し折口信夫が深く理解協力した日本民俗学は、広義の歴史学であり、その基本は伝承論であり変遷論であった。1983年開館の民俗学の唯一の国立研究機関たる国立歴史民俗博物館創設の基本理念も、文献記録を資料とする文献史学、考古遺物を資料とする考古学、民間伝承を資料とする民俗学、この三学協業を中心としてさらなる学際協業を進め新たな広義の歴史学を構築することにあった。民俗学はその広義の歴史学を支える鼎の確かな一本としての社会的責任がある。
「民俗学は「変化」をどうとらえるか」という問題設定がその意味で的確なものであることをここに確認し、民俗の「変化」については、三つの視点があることを指摘しておきたい。第一は、柳田國男の重出立証法(民俗資料の性質をふまえた上での文献史学の単独立証法と対比される方法)と、方言周圏論を典型例とする遠方の一致などの民俗分布解釈論(重出立証法に対応する一つの解釈方法)による把握のしかたである。これは列島規模での生活変遷を通史的にまた地域差や階層差をも含む動態的で立体的な視点から把握しようとした斬新な歴史探究構想にもとづくものであった(『蝸牛考』、『郷土生活の研究法』、『先祖の話』他)。もちろんこれは欧米のフォークロアやフォルクスクンデとは異なる日本民俗学の基本的な視点であり、その継承研磨発展の可能性を秘めている重要な視点と方法である。第二は、新谷がかつて提示した、近現代日本の民俗伝承についてのα波(伝統波)、β波(創生波)、γ波(大衆波)が併走しつつ展開するという三波展開論である。農業や漁業など生業活動におけるα波(人力・畜力)→β波(機械力)→γ波(β波の大衆化)、婚儀や葬儀など儀礼におけるα波(自前処理と相互扶助)→β波(荘厳化と商品化)→γ波(β波の大衆化)、という三波展開が繰り返されるという小さな仮説である。(「葬儀の近代」『都市と暮らしの民俗学』2006、「AGEING JAPAN AND THE TRANSMISSION OF TRADITIONAL,SKILLS AND KNOW‐HOW」.“The Demographic challenge :A Handbook about Japan”, Brill Academic Publishers,pp.561-pp.569 2008。)第三は、高度経済成長による生活の革命的変化に対する民俗学の対応方法としてビフォアー・アフターを丹念に観察分析するという視点と方法である。高度経済成長期の技術革新や燃料革命に始まり、その後グローバル化やバーチャル化が加速度的に進んでいる現代社会における生活変化を前にして、民俗学は何ができるのか、その有用性と存在意義を考えようという視点である。それは、高度経済成長期以前の伝統的な生活の中には存在しなかった生活便利品、古くはテレビや洗濯機、今ではパソコンや携帯など、柳田や折口の時代には存在しなかった生活用具や生活環境を前にして、技術と意識の伝承と対応とが、個々の現場的にまた列島規模的に、どのようになされているのか、へと注目する視点である。新しく生まれ定着してきている歳時習俗や娯楽芸能などにももちろん注目する。
2010年のこの仙台でのプレシンポでは、とくにこの第三の視点を中心に、問題への接近方法を検討してみることにしたい。その第三の視点では以下の三者をともに対象とすることが重要であることを説き、(1)喪失する民俗、(2)変容する民俗、(3)新生する民俗、に分けてそれぞれの作業例の一部を参考として紹介してみる。
(1)喪失する民俗に対して
=研究者の世代責任感覚から(その習俗へのリアリティのある最後の世代として)
例 自分の例では、両墓制研究、御鳥喰習俗の研究、嫁叩き習俗の研究など、他にももちろん多くの研究者の業績あり
(2)変容する民俗に対して
=目撃者世代
例 『葬儀と墓の現在』2002(福沢・米田・関沢ほか)
「足元からみる民俗(1)−(18)」(『仙台市歴史民俗資料館調査報告』第11集−第28集、佐藤ほか)1992−2010、
「墓郷・宮郷・水郷をめぐる民俗学的考察」『宮座と墓制の歴史民俗』2005(関沢)、
「民間伝承の「危機」と民俗学」『近江学』2 2010(米田) など他にも多い
(3)新生する民俗に対して
=目撃者世代
例 『ふるさと資源化と民俗学』2007(岩本ほか)
『高度経済成長と生活革命』2010(岩本・関沢・湯川ほか) など他にも多い