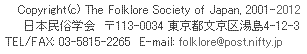HOME > 談話会開催記録 > 2010年 > 第851回
談話会要旨-第851回(「さらば『民俗学』―新しい《民俗学》の再構築に向けて(6) ドイツ民俗学案内−)
ドイツにおける民俗学教育―ハンブルグ大学での見聞から―
山 泰幸(関西学院大学)
2008年12月27日〜2009年1月4日の日程で、ドイツのハンブルグを訪問した。目的は、ハンブルグ大学終身教授であるアルブレヒト・レーマン氏に面会すること、およびレーマン氏をリーダーとして推進されてきたハンブルグ大学の語り研究プロレジェクトについて理解を深めること、そしてハンブルグ大学民俗学研究所の図書室を見学することであった。
ハンブルグ大学を訪問したのは、岩本通弥、法橋量、山泰幸の3名である。私が訪問することになったのは、岩本氏から参加を呼びかけられたことがきっかけである。数年前より、岩本氏からドイツ民俗学の現状について何度か話をうかがう機会があり、日本における民俗学の学問的イメージでは捉えきれないような、ドイツの民俗学の現状を知り、一度、直接、確かめたいと願っていた。私が関心をもっていたのは、ドイツ民俗学の学際性であり、理論的・方法論的な展開であった。特に、哲学(現象学)や社会学との理論的・方法論的な影響関係であり、それを反映した教育プログラムなどであった。また、ドイツ民俗学の専門家である法橋氏が案内をしてくださることもあり、滅多にない機会であり、参加をさせていただいた。
アルブレヒト・レーマン氏は、主に語り研究の領域において、膨大な業績を積み重ねてきた、現代ドイツ民俗学を代表する研究者の一人であり、理論・方法論において独自の展開を遂げてきた。ハンブルグ大学でのインタビューによれば、「語り」を重視するレーマン氏の理論の背景には、ハイデッガーの哲学の強い影響をあること。具体的な研究の方法論は、フッサールの現象学をベースにして、現象学的社会学の展開との関連性を見ることができるようである。特に、アルフレッド・シュッツやトーマス・ルックマンとは強い影響関係があると考えられる。この点は、今後、レーマン氏の研究が日本でも紹介され、研究される際に、注目すべきポイントになると考えられる。
ハンブルグ大学の語り研究のプロジェクトに関しては、データアーカイブの保管室を見学した。データは録音テープと面接調査の記録ファイルというかたちで保管されていた。被調査者ごとに、医者のカルテのように、詳細な記録がされていた。特に、興味深かったのは、態度や表情、雰囲気など、面接時に被調査者から受けた印象を書き込んでいることである。心理療法家のように、その人の存在感から全体的に捉えようということのようである。
民俗学研究所の図書館では、授業ごとに課題図書や論文が指定されて、論文はファイル化され整理されて課題図書とともに授業担当教員ごとに本棚に整理されていた。課題図書の分野としては、民俗学を中心に、民族学、人類学、社会学、カルチュラル・スタディーズ、メディア論、博物館論などがあった。取り上げられているテーマは多岐にわたり、身体、スポーツ、ダンス、病い、映画、映像、消費社会、労働、メディア、マスコミ、コミュニケーション、インターネット、流行、キッチュ、動物、ユダヤ人問題、近代史などである。日本で言えば、広い意味での「文化の社会学」に重なる研究領域ということができるだろう。
注目したいのは、理論や質的調査の方法論に関する課題図書が多くみられたこと。現代社会研究としてのスタンスが明確こと。社会学の影響が見られたことである。ピエール・ブルデューの「ハビタス」概念を特にテーマに取り上げている授業が見られたことは目をひいた。隣接分野の理論・方法論を積極的に取り入れながら、現代社会研究として一つのスタイルを確立しつつあるドイツ民俗学の一端を垣間見ることができた。
ドイツにおける民俗学/ヨーロッパ・エスノロジーの展開―テュービンゲン、マールブルグ、ゲッティンゲンを中心に―
森 明子(国立民族学博物館)
ドイツの民俗学研究は、政治や経済、社会の動向と深く関わって展開してきた。ファルケンシュタイン会議(1970)は、戦後の民俗学のターニングポイントを象徴的に示すキーワードである。だが、冷戦下の経済復興から、社会運動、大学制度改革、東西ドイツ統一を経て現在に至るドイツの民俗学が展開してきた過程は、学会よりも、それぞれの大学研究所における動向を個別に見ることによって明らかになる点が多い。本発表では、ドイツの民俗学研究の展開の過程を、個別の大学研究所の縮尺で、政治的、社会的文脈とあわせて示すことを目的とした。この発表は、2009年度に終了した科研費研究「戦後民俗学の展開に関するドイツと日本の比較研究―社会における学問実践の形」(研究代表者、森明子)をもとにしている。以下では、重要な転機となる三つの時期にしたがって要約する。
ドイツの民俗学の研究と教育は、20世紀前半までゲルマニスティーク(ドイツ語・ドイツ文学)のもとにあり、1930年代にナチスが政権をとってから、大学講座として独立するようになった。初期に講座を獲得したのは、テュービンゲン大学とベルリン・フンボルト大学で、ナチスの意向に添うことで、大学での地歩を固めた経緯がある。ナチス崩壊後、テュービンゲン大学の民俗学研究所は閉鎖され、50年代後半になって再開されると、当初から脱ナチズムを至上命題とすることになった。ベルリン大学は、東ドイツに属して、西側の民俗学とは別の道を歩むことになった。一方、ゲッティンゲン大学では、「クリーンな」(ナチスによごれていない)ポイカート教授のもとに、戦後すぐに授業が再開されたが、研究はナチス以前の1920年代の民俗学研究に回帰することになった。
民俗学の大きな変革は、1960年代から70年代にかけて起こった。ドイツ社会全体がナチズムの暴走を許した過去を批判し、1968年革命へむけて動いていたなかで、民俗学のあり方も根底から問い直された。70年代初頭の大学改革は、こうした議論の果実を制度に反映させることで、学の革新に一役買うことになった。テュービンゲンでは、バウジンガーが中心になって、ナチズムと結んだ過去の民俗学を批判し、研究対象を見直すとともに、科学的な理論と方法を模索し、社会科学へと接近していった。研究所は、大学改革を機に「民俗学」から「経験文化科学」へ名称変更し、社会科学・行動科学のもとに再配置された。マールブルグの民俗学は、1960年にゲルマニスティークから独立し、ハイルフルトのもとでゲルマニスティークと社会学のあいだとしての民俗学研究を推進し、1970年の大学制度改革を機に「ヨーロッパ・エスノロジーと文化研究」と名称変更した。一方、ゲッティンゲンでは、ランケのもとに大プロジェクト「メルヘン百科事典」がはじまり、古典的な語り研究によって世界に知られることになった。
1989年のベルリンの壁の撤去とともに、ドイツの政治・経済・社会状況は大きく転換した。社会科学へと接近していた民俗学はその方向を、80年代末以降、文化研究へと大きく転回しながら、これまで蓄積されてきた研究に連続させようとしている。テュービンゲン大学では、勇退したバウジンガーがなお大きな影響力をもちつづける一方、オーストリアからヨーラーとチョーフェンが迎えられ、文化科学・文化研究への方向を明確に打ち出している。マールブルグでは、スペインをフィールドとするブラウンのもとに、フェルカークンデ(民族学)や宗教学との協力体制が進み、巨大なアーカイブを擁してメディア研究にも強みを発揮している。ゲッティンゲンは、ペンシルベニアで教鞭をとっていたベンディクスを迎え、多彩なプロジェクトを展開して、新しい局面を切り開きつつある。
現在のドイツの民俗学/ヨーロッパ・エスノロジーの研究テーマは多岐にわたっていて、テーマから学問の境界線をひくことはできない。この学を規定するのは、対象の切り取り方、研究対象に対する姿勢であり、とくに「経験的方法」と呼ばれる接近方法である。後者は、ドイツやUSAの民俗学に、文化人類学や都市社会学の蓄積も取り込んだ、独自のフィールドワーク論である。
ヨーロッパ・エスノロジーという名称が明示するとおり、民俗学の対象は、もはや国ではなくヨーロッパであることが宣言されている。キーコンセプトの郷土は、文化資源や環境という概念をともなって、グローバルなパースペクティヴのもとに再配置され、テーマ化される。ドイツの民俗学/ヨーロッパ・エスノロジーは、隣接科学との境界をつきやぶって、さらに学際的な領域に展開する過程にある、と私はとらえている。
【PDF】参考 http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/bitstream/10502/3365/1/KH_033_3_005.pdf