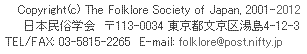HOME > 談話会開催記録 > 2009年 > 第846回
第846回 日本民俗学会談話会
シリーズ・さらば「民俗学」―新しい《民俗学》の再構築に向けて―(4)」
海外学者の日本文化研究について―イエ・モデルの形成過程
桑山 敬己(北海道大学大学院 文学研究科)
一口に「海外」と言っても広いので、対象を英語圏の人類学と社会学に限定して主にイエの研究を扱う。ここでいうイエとは、長と後継者の継承線を構造の核として、家名や位牌に象徴される超世代的連続を理念とする日本の伝統的集団である。中世以降、イエは時代・地域・階級・職業などの差に柔軟に適応して、家族集団として存続してきた。第二次世界大戦後の民法改正によって廃止されたのは明治民法が制定したイエ(いわゆる「家制度」)であって、イエそのものが消滅したわけではない。事実、儀礼の場におけるイエ意識には今日でも強固なものがある。英語圏では、family, house, household などと訳されてきたが、意味が微妙にずれるので、そのままローマ字で ie と表記することも多い。
最近でこそ、英語圏の学者はアニメやマンガやコスプレなど、現代の大衆文化を取り上げるようになったが、一九三〇年代から八〇年代までの焦点の一つはイエであった。概して、彼らはイエを日本的集団の原型と捉えて、(一)より大きな集団をイエの構造的拡大とみなし、(二)イエと個人の一体感やイエのための個人の犠牲を強調した。当然、そこには理念化された西洋の個人主義との対比があり、《日本=集団主義》という前提があったことは明らかである。私はこうした枠組みを「イエ・モデル」と呼んでいる。
イエ・モデルはさまざまに応用されたが、一例としてコミュニティー研究を取り上げてみよう。まず農村研究から始めると、この分野の先駆的業績はエンブリー(J. Embree)のSuye Mura(一九三九)である。エンブリーは構造機能主義の創始者ラドクリフ=ブラウンがシカゴ大学で教えていたときの学生で、彼の本は当時の英語圏人類学でもっとも影響力の強い理論的枠組みで書かれた。その第三章 “Family and Household” の冒頭には、イエは部落生活の基本的社会単位であり、部落の行事に参加する単位は個人ではなくイエであると書かれている。またイエには共同的統一があり、その意思は個人の欲求に優先すると述べられている。重要なことは、戦後に日本の農村を調査したアメリカの学者は、ほぼ例外なくエンブリーの見解を踏襲したという事実である。たとえば、一九五〇年代に岡山市に設立されたミシガン大学日本研究所の面々(代表的人物として R. Beardsley, E. Norbeck, J. Cornell)は、個人を超越した存在としてイエを描いた。彼らの著作は本格的な産業化が始まる前の日本の貴重な記録であるが、残念ながら日本ではその存在すら知られておらず、今日アメリカでも振り返られることは少なくなっている。
次に都市研究に目を移すと、ドーア(R. Dore)のCity Life in Japan(一九五八)が光る。この全二四章からなる大著の第二部(八章から十一章)のテーマはイエと家族で、イエは超世代的存在で永続を目的とすること、個人はイエの代理かつ一時的構成員にすぎないこと、戦後の民法改正にもかかわらず日本人のアイデンティティはイエと密接に結びついていること、などが書かれている。同様の見解はヴォーゲル(E. Vogel)のJapan’s New Middle Class(一九六三)にも見られるが、注目すべきは、両者とも日本の学者の著作を幅広く参照しているということである。その中には穂積陳重が英語で書いたAncestor?Worship and Japanese Law(一九一二)が含まれている。
実は、この点は農村研究も同じであって、前述のエンブリーはフィールドに赴く前に柳田国男や鈴木栄太郎と会って、多くの情報を得たことが序文に明記されている。周知のように、柳田は日本人にとってのイエの重要性を幾度となく説き、鈴木は『日本農村社会学原理』(一九四〇)でイエは一つの「精神」であると述べた。さらに時代を遡れば、柳田は学生時代に穂積陳重の弟である穂積八束の講義を聞いていたらしく、八束は民法典論争において、キリスト教に由来する西洋的個人主義は、祖先を重視する日本の家族主義とは相いれないという論陣を張った人物である。《西洋=個人主義》《日本=集団主義》という二項対立的理解の原点の一つは、彼の思想にあると言ってよい。その後、一九一〇年代には家族国家論が修身の教科書に登場するが、イエの永続について柳田が語った『時代ト農政』(一九一〇)の刊行は、それとほぼ時を同じくしている。
イエを日本人の精神や性格と関連づけて理解する試みは、第二次世界大戦後には有賀喜左衛門や中根千枝らに引き継がれたが、ほぼ一貫して日本の学界の主流を形成した。もちろん、丸山真男、川島武宜、福武直といった戦後リベラル派はイエを徹底的に攻撃したが、皮肉にもそれは日本におけるイエの重要性を裏付けることになった。
このように考えると、イエ・モデルは英語圏の学者が作り出したというより、日本の学者との「共謀」の産物と言えよう。つまり、エンブリーの時代から彼らは日本人と知的交流があり、自覚的であろうと無自覚的であろうと、日本人のイエ言説を参照しながら現地で資料を収集していたのだ。
今日、日本のさまざまな現象を研究するために日本を訪れる海外の学者にとって、日本をフィールドとする民俗学者は彼らにとって最適のパートナーとなりうる。はたしてどのような交流が行われるのか、またそれ以前に、語り合う心の準備があるのかどうか、かつての「二つのミンゾクガク」の片割れである民族学者の私は興味深く見守っている。
脱領域的な日本文化研究について―わたしの経験から―
クネヒト・ペトロ
個人的な経験が話の中心になるが、本発表では以下の主な3点について触れることにする:1)自分の日本文化研究の成り立ち;2)日本人による日本文化研究に関する幾つかの問題点;3)領域の限界を乗り越えようとする一つの試み。
日本文化に関する私の関心の芽生えはもう50年ほど前の、ギムナジウム(高校)の最終年に遡る。その頃、日本とその文化は「憧れの的」に過ぎなかった。それから10年ほど後に、私は宣教活動の目的で日本に渡り、実際にその文化に触れる機会を得たのだった。語学の勉強の傍ら、少しずつその言葉の源である日本文化について勉強し始めた。結果的にいうと、宣教活動より日本文化研究への関心が次第に強くなったために、研究活動を自分の道として選ぶことになった。
大学紛争が終わり授業も再開した折、東大で文化人類学の研究を始めたが、自分は研究室の中で、二重の「異人」的存在だと感じていた。第一に日本の大学の雰囲気に不慣れな外国人だったからであり、第二に、主として海外諸民族が研究対象になっている研究室で、自分は日本の民俗文化を研究しようと思っていたからである。文献資料研究も文化研究の一つの道だが、生きている文化に直接触れることこそ、私にとって特に重要だと判断し、フィールドワークをする機会を求めていた。運良くその機会を東北のある山村で得たのだが、具体的に予測しかねた幾つかの問題が起きしまった。色々な紹介のお陰で村人は大いに協力してくれたが、それは主に形式的な協力にすぎなかった。そのことが、下宿探しの作業を通して明らかになった。数ヶ月間かけてやっと下宿が決まったが、その頃から村人との付き合いは徐々に親しくなっていった。親しさが深くなるにつれて、得られた情報内容も濃くなった。それに伴い、もう一つの問題が生じた。それは村人、特に老人たちの方言だった。方言理解に苦しんでいるのに気づいた下宿の老婆が、その後良き案内役になってくれたので、私の調査は一段と楽になっていった。
第三の問題は村の慣習だった。東京で既に覚えていた「日本の習慣」は当然、東北の村でも通用すると思ったが、必ずしもそうではないことが、様々な苦い経験を通して学んだことだった。これらの経験で、「日本」とは決して隅々まで統一された文化ではないと思うようになった。この点は、別な側面でも教えられたことだった。
日本の文化の本質は、他所からやってきた外国人には理解しがたいものだと、割とよく言われる。確かに日本人研究者は日本語を母国語にしているわけだから、言葉上、外国人のようなハンディがないように見える。しかし村の調査にやってきて、老人を相手にして話を聞いた大学生に対する、地元の老人たちの評価は実に厳しいものだった。そもそも普通の村人の話し方を理解するのに苦労が多いのに、老人たちの話はもっと方言が強い。それなのに日本の研究者や学生が、老人たちの話をほんとうにわかっていたのかどうか疑問だと、私は言われたことがある。もう一つの問題は研究課題である。民俗学者は調査に出掛ける前に研究課題を決めて、それを中心に調査を行う傾向がある。調査の時間的限界もあって、研究者は前もって決めたテーマについて、できるだけ沢山のデータを得ようとする。しかし質問された相手が、そもそも研究者のテーマに関心があるとは限らない。従って、地元からは「先生は自分のことしか考えず、我々のことを少しも考えてくれない」という批判が出るのである。このように話し相手の生活事情などに気を配る余裕のない短期調査の研究者に、たとえ日本人だとはいえ、日本の村の文化について一体どれほどの理解できているだろうか、私は疑問に思うのである。ある村、ある地域は、日本の村、日本の地域なのだから、日本人なら外国人よりもその特徴がよくわかると、ほんとうに云えるのだろうか? 相手が大事にしている言葉、習慣など、研究者にうまく通じなければ、その理解に問題があるような気がしてならない。
更に、このようにして理解不十分で入手した資料を他の資料と比較しようとするとき、一体どんな比較が可能だというのか? 万一比較できたとしても、それはせいぜい研究者が限定し決めつけた、ある文化現象だけだろう。しかしそれでもなお、それは地域の独特な事情のなかで存在している現象と、他の地域の似ていると思われる現象との比較であり、果たしてそれは比較になっているだろうか? 抽象化された現象そのものは、研究者の作った比較基準で比較できるにせよ、それが置かれている事情や背景までを、比較するのは難しいのではないだろうか?
最後に、領域を超えようとする民俗学の一つの試みを紹介したい。1942年、北京の輔仁大学で、当大学付属の東洋民族学博物館の出版物として、『民俗学誌』(Folklore Studies)という雑誌が創刊された。創立者兼編集担当者はMatthias Ederであった。Ederはこの雑誌を、特定文化や国などを問わず、民俗学を研究している学者等の研究成果と議論の交換の場として考えていたので、英・独・仏の3ヶ国語を雑誌の公用語として認めていた。つまり彼にとって、民俗学とは学問の一分野であり特定国で研究材料を求める学問であっても、その分析と理論のレベルにおいては、一国の限界を乗り越える素質を十分に有した学問として認識されていた。後に雑誌は『アジア民俗学誌』(Asian Folklore Studies) と改名し、それに伴って雑誌が扱う地域はアジアに、使用言語は英語に限定されたのだが、国際的な研究者陣が資料と研究成果を交換出来る場を提供する、という意図には変わりがなかった。この雑誌の約60年間の歴史において、論文などを発表した日本人研究者も決して少なくはなかった。従ってこの雑誌は、日本民俗学が日本という領域を世界大的に紹介するという、見逃せない役割を果たして来たことも絶対に忘れてはならないことである。