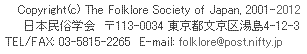HOME > 談話会開催記録 > 2010年 > 第848回 > A会場|B会場|C会場
談話会要旨-第848回(2009年度 民俗学関係卒業論文発表会)A会場
周りに生かされる暮らし
秋山 みほ(日本女子大学人間社会学部文化学科)
私の卒業論文は、新潟県村上市、川の最奥にある山村、「高根集落」をフィールドとして、女性三代のライフヒストリーの聞きとりから、高度経済成長期以前、最中、以後の暮らしの変遷とその関連を明らかにしようとしたものである。
研究方法は現地での聞き取り調査を基本とし、主に高根のS家女性3代(大おばあさん(大正6年生まれ)、中おばあさん(昭和14年生まれ)、奥さん(昭和37年生まれ))にお話を伺った。
まずは聞き取りから高度成長期以前の年間の仕事を年表に起こした。集落内でほぼ自給自足でまかなえていたことが分かった。
次に私自身も参加した共存の森ネットワークの棚田調査を利用して、現在と未来を明らかにした。過去と現在では、自給している種類と量に変化があったものの、「自給的価値観に代わりがないことが分かった。
次に高根の女性の暮らしがどのように変わっていったかを年表に落とした。暮らしの電化など変化が分かったが、昔と今と変わらないことも見つかった。それが「嫁と姑の役割分担」だ。高根では姑が子育てをする。S家でも中おばあさんが子育てをしている。「若い人には若い人の仕事がある。自分も農作業で忙しい時、そうしてもらったから、あたりまえの感覚。」ということだった。つまり「若い人の仕事」の中身は変わってきているが、役割分担とお互いの仕事に対する理解は変わっていない、という事が分かった。
また、変わっていない事のもう1つとして風祭の奉納相撲も挙げたい。この奉納相撲では屋号をよく見かけた。「家」「家長」「集落のつながり」が垣間見えた。またこの相撲について時代とあわないと感じる人もいるものの、この相撲自体なくなる、と考えてはいないように感じられた。
この論文では、過去と現在で様々なことが変わっているものの、「ここにいる人たちで、ここにあるもので生きていこう」という基本方針が変わっていない事が分かった。
阿賀野川における筏流しと筏乗り
佐藤 辰生(新潟大学人文学部地域文化課程)
これまでの筏流しに関する研究では、阿賀野川を対象とするものが少なかった。そこで卒業論文ではかつて阿賀野川において筏流しを行った筏乗りと、筏流しを請け負わせていた山師の2人から聞き書き調査を行い、筏乗りと山師の関係性も含めた上で、阿賀野川における筏流しと筏乗りの特徴を明らかにしようと試みた。時代は筏乗りの人が筏流しを行った昭和25年頃から昭和36年を設定した。
阿賀野川における筏乗りは主に新潟県東蒲原郡に在住し、この地域で材木屋を経営する山師の請負によって筏流しを行った。筏流しは一年を通して行えたが、筏の仕事がないときは山師の山仕事を手伝って生計を立てていた。筏乗りになる条件は特になく、筏の組に所属することで筏乗りとなることができたため、筏乗りらは集団として行動をともにした。
阿賀野川の筏流しの特徴として、筏の中継地である津川を基準として上流を「上川筏」、下流を「下川筏」という。両者は河川環境が異なるため、筏流しの行なう季節・賃金も異なる。下川筏は筏1房ごとで収入が決まり、上川筏と山仕事は日当として1日に働いた人数によって収入が決まった。川の水量が増えたとき、臨時に筏に乗って収入を得ることもあった。得た収入は筏の組のオヤカタによって集められ、諸経費を引いたものを組の人数で割って個人の賃金となった。そのため、筏乗りの賃金の額は、筏流しの経験年数や技術の有無などに左右されなかった。
このような筏乗りに賃金を支払ったのは山師であった。山師には専属の筏の組というものがあり、そのような組とはシンセキのように付き合い、密接な関係性のあることが指摘できた。しかし昭和36年の揚川ダム建設によって筏流しが終焉を迎えると、この関係性も消滅した。筏乗りと山師の関係性というのは個人対個人ではなく、筏乗り対山師という構図で成り立っていたのであった。
養蚕農家における雇い入れの形態とその変遷
関根 里美(新潟大学)
出稼ぎに関する研究はこれまで農村や漁村から出ていく出稼ぎの実態とその衰退の研究に重きが置かれてきた。出稼ぎはその期間と時期から年間で雇われる形態とある季節にのみ雇われる形態に分類される。本論の調査地の農家において年間で雇う形態はバントウ、季節的に雇う形態には養蚕に関する雇いのカイコビヨウ、麦刈りから田植えの時期の雇いの季節労務者、田植えのみに雇うスートメ、ウケトリがあげられる。季節雇いの中で群馬県において養蚕の出稼ぎのカイコビヨウという特徴的な雇いの形態がみられる。このことについてはこれまでも指摘されてきているが、この問題について十分な分析がなされていない。また従来の出稼ぎ研究では雇う側からの視点が欠けていることから、本論では季節雇いが農家にとってどのようなものであるのか、戦前から戦後にかけてどのように変化するのかについて明らかにしたい。
群馬県内のカイコビヨウは県内での移動が多くみられ山間地域から平坦地への移動が特徴としてみられる。調査地の南大類は高崎市の南西部に位置し平坦な地形で、農家は稲と麦の二毛作を行っている地域である。南大類でも戦前のカイコビヨウは桂庵を通じて県内の山間地域から来ていた。戦後、食糧増産の影響を受け養蚕の飼育量が減少したことを受けカイコビヨウは衰退し、桂庵を通じて山間地域から来ることはなくなり近所から人足を集めるようになり、現在では上蔟時に近所の非農家に手伝いを頼むという形で残っている程度である。養蚕以外で農業に関する雇いは、戦前は桂庵を通じて県内・県外の各地から来ていたが、戦後各地の桂庵が消滅したことによってその人足の確保は農協の斡旋へと変化し、農業に機械が普及されるまで続いた。
全島避難が生んだ「島民意識」−三宅島復興期におけるつながりの形成−
山代 知(成城大学文芸学部文化史学科)
地方都市や農山村において過疎化や限界集落化への対策の一環として地域住民によるコミュニティの再生が議論されている。全島避難によって一度コミュニティが崩壊した三宅島の現状を明らかにすることで、こうした議論の一助になるのではないかと考えた。
本論では三宅島の現状について取り上げると共に、全島避難を契機として島民たちが「島民意識」を共有していきながら島の復興に尽力する現状をとりあげているが、発表はこの中でも特に後者にあたる「島民意識」の共有とそれに伴う変化を中心にとりあげる。
調査地である三宅島には2000年の噴火以前、5つの集落が存在したが、各集落はほぼ自給自足の環境を持ち交流が少なかったため、島民達はその帰属意識をあくまで居住する集落においていた。ところが全島避難によって既存のコミュニティが崩壊し、代わりに避難民の連絡会や帰島運動を通して集落を超えた島民規模での交流が新たに生まれ、これが「島民意識」の共有を促すことになった。一方で、帰島運動を通して、困難を知ってなお帰島を選択する人と、帰島を断念する人が生じた。
2005年の帰島開始後は、帰島を選んだ人々は避難中の経験と交流をいかして積極的に「本土の人」と協力して生活環境やインフラ、産業の復興が進められている。また、学校の統廃合によって島内の子供世代やその保護者達の横のつながりも強化された。「島民意識」を共有が進んだことで、現状についてきちんと議論しあえる素地がうまれたと同時に、島外の人間を招いて活動してもらうだけの余地もうまれたのである。
本論文は三宅島の今を捉えつつ、「島民意識」の共有を切り口として島の変化を明らかにする事には一定の成果を収めたものの、定性的なデータが大半で定量的なデータに乏しいことや、避難当時の島民の動向、現在もなお帰島していない島民の動向に関する調査・分析が不十分であるといった点で課題を残した。
ハマに生きる女たち−茨城県北茨城市大津地区を事例として−
上久保 都生子(筑波大学第二学群比較文化学類)
本論文の目的は、茨城県北茨城市大津地区の漁村における女性の役割や意識、在り方を明らかにし、それが生業や漁師たちを含めた漁村全体とどのように関係し、変化してきたのかについて、女性の姿を中心に考察することである。これまで、漁村や漁業を対象とした研究の多くは、漁師の漁撈形態や漁撈方法、またその民俗的信仰など、男性のかかわる領域に焦点を当ててなされていたものが多く、女性という存在には若干弱い印象を付加されて記述されることが多かったと論者は考える。
漁村における女性の姿を考察するために、論者は大津地区漁村でフィールドワークを行い、そこで得られた調査内容を中核に記述を行った。大津地区は、茨城県最北端の市の東側に位置し、かねてから漁業によって繁栄をしてきた地区であることが史料からうかがえる。しかしながら、現在深刻な過疎化と高齢化によって漁業が衰退の傾向にある地区である。
本論文は5章から成り、第1章では社会学・経済学的視点、および民俗学的視点から先行研究を整理した。第2章で大津地区の概況を述べ、第3、4章においては女性を取り巻く環境を夫である漁師を中心に描いた。そして、第5章で「ハマに生きる女たち」についての考察を試みた。
漁村女性の存在は木村都により周縁的で「みえない」存在 とされてきたことが指摘されているが、それは変わりつつある。「予定のない」漁業を支えるハマの女たちは、ある強さを持っており、自ら環境を変え、意識を変えていこうというその強さが向かう先は、男性と女性、大津地区の住民たちの共存的な場を作り出す方へ向いている。それが作り出してきた漁村住民の共通認識や男女の関係がかかわりあう空間が漁村としての大津を存続させる要因になっているとも推測できるのである。
海女の存続とその可能性 ―三重県鳥羽市相差町の事例―
中村 亜美(慶應義塾大学)
漁撈民の中でもアマと呼ばれる人々は、裸に近い恰好、現在ではウェットスーツを着用して潜水し漁を行うことを生業とする。日本では全国的に分布、さらに国境をまたぎ韓国の済州島においても、今なおその姿が見られ、またこれに従事する女性が確認できるのは両地域のみになる。アマに関しては民俗学、社会学、考古学、医学など広い学問領域にわたり、多くの研究成果が積み重ねられた。中でも民俗学的な研究は、漁撈文化が日本文化の形成に深く関わるとし、先史時代まで遡及可能な「原始的な」古来の生業形態を持つアマと、その民俗、文化を収集、分析することによってその淵源を探ることに比重が置かれてきた。本稿では本来の民俗学的アマ研究の目的からはやや離れるが、現在の海女の営みについて調査し、この伝統的と言えばあまりに伝統的な生業の、現代以降の存続の可能性について論じる。
日本においてアマの分布を俯瞰したとき、男性アマと女性アマが住みわける乃至、混合する不可解な性別分業のありようが見える。ジェンダーの問題はアマにまつわる大きな疑問として解明されえぬままだが、女性の海女が何故誕生したかではなく存続しえたか、海女自身の価値観に準じて論じることは可能である。
古代から連綿と続く生業の海女が、近現代に至って急速に解体されつつある背景には、西洋的な労働概念の浸透と価値観の推移に伴い、辛く危険な「労働」として海女を回避する言説がある。海女を続ける、また新しく海女になる、当事者の側は、言説に自ら言及、寄与しながらも、一方で海女の喜びという動機を確かに保持している。その内容を、誇り、連帯、遊び、海の特質として本稿では分析した。年齢階梯制に支えられたいわば縦型の漁村社会のシステムの中で、海女は横断的で柔軟なシステムを体現する。
これらのことを踏まえ、生業、観光業、マイナーサブシステンスの、内発的な3つの観点から、海女存続の可能性を検討した。
捕鯨の語られ方
末 恵理香(慶応義塾大学文学部)
今もなおタイムリーな話題を提供し続けている捕鯨問題。それを一定の論や歴史の上で語ることは不可能なことは言うまでもない。そこで「鯨はいかにして語られてきたのか」という問いを設け、重層的な捕鯨の歴史や捕鯨問題の本質を、多くの言説を拾い上げて明らかにする。具体的には、「祭祀の中でのくじら」や「鯨肉といった形で戦後に普及したくじら」が日本でどのような形で存在してきたのかを検討し、今後の方向性を示していく。
そこでまず、「捕鯨モラトリアムから20年余たった現在、果たして捕鯨文化なるものは存在しているのか。もし、存在しているとしてこれを日本人全体が共有している文化といえるのだろうか。」という仮説を立て、日本における捕鯨の歴史の中で日本における捕鯨の歴史を概観していく。そのうえで、和歌山県東牟婁郡太地町のフィールドワークと、三重県四日市市富田地区鯨船神事を例に「捕鯨文化」を考える。
特に今回の発表では、「語られ方」という切り口で、今もなお糸口の見えない捕鯨問題において、なぜ西欧諸国の人々は反捕鯨の立場をとるのかを検討する。その理由を、動物権運動や西欧と東洋の自然観、鯨に対する扱い方の違いを考える。また、環境保護団体グリーンピースのインタビューもここで取り上げる。
考察では、捕鯨問題を本当に解決しようとしている人々がいるのかを検証する。商業捕鯨禁止のモラトリアムから21年たった今、捕鯨従事者の高齢化が進む中で、捕鯨が継承されているのか、鯨肉給食の復活にも触れていく。反捕鯨、親捕鯨といった二項対立ではどうしても政治的な文脈に終始し、主語が「日本人」という曖昧で大きなものに拡大しがちだ。それとは一線を画し、「そこに生きる人々の財産」として捕鯨を捉える。今後の捕鯨再開の意義を、ローカルカルチャーの尊重、地域活性化という面において考える。