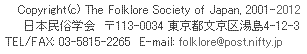HOME > 談話会開催記録 > 2010年 > 第848回 > A会場|B会場|C会場
談話会要旨-第848回(2009年度 民俗学関係卒業論文発表会)B会場
道中日記からみる江戸の食文化
戸塚 妙子(東京家政学院大学)
江戸時代盛んだった山岳信仰は人々にとって大きな人生儀礼を兼ねたものであり、とくに伊勢参宮は庶民にとって人気のある聖地であった。その中で「道中日記」「小遣い帳」といった旅日記から地域の名物や名所が記されており、今でも貴重な郷土資料として扱われる。
近年の道中日記研究は歴史学や地理学からのアプローチが顕著的であり、さらにこれまでの研究の多くは、新城常三氏の『社寺参詣の社会経済史的研究』(塙書房・1964年)に代表される社会経済史的側面からの道中日記の数量分析や、歴史学、観光地域学、民俗学から見ることが多く、道中日記から「食」への研究を広げることはあまり行われていない。食文化という過程の中で『江戸時代の食文化』としてひとくくりにされる事は多いが、今回ではゼミの担当教員が所蔵している道中記という個人の日記から、「食」と「旅」の繋がりや食文化をみていくことを試みた。
今回紹介した史料は、「天保二年 富士登山日記覚書 」(以下史料1)と「安政二年卯歳 冨士道中小遣覚書帳 」(以下史料2)の二点の古文書であり、いずれも西海賢二教員が所蔵しているものである。この資料は約20年違いに書かれた道中日記だが両資料とも「富士信仰」を目的に記されたものである。
二十年違いの道中日記だが、旅の仕方はほとんど同じであった。まず、大きな峠の前後では必ず「白さとう」を購入している。この時代、砂糖は薬屋で手に入れるということもあって疲れには甘いものが効くという考えはこの時代からあったようだ。同時に「焼酎」も度々購入されていたが、口にする酒ではなく、疲れた時に足に吹きかけるというこの時代ならではの旅の知恵だった。
また、参考史料から東海道沿いの名物をあげたところ山中では甘い茶菓子・海沿いは魚・海から離れた場所にはうどん、染め飯、とろろ汁など魚を使わない物が特徴的で、ここでも「食」「地域」「旅文化」の繋がりが表れていた。
祈願行為と現代日本人~合格祈願グッズとお守りの諸相から~
内海 彩子(首都大学東京)
日本人の信仰や宗教観の特徴のひとつに現世利益があるといわれている。わたしたちの日常の行動や年中行事など、多くの行動には何かしらの祈願が込められている。祈願に焦点をあてることは、私たち日本人を知る上でひとつの手掛かりになるのではないか。
今回きっかけとなったのは以下の素朴な疑問である。
①近年販売されている合格祈願の菓子商品はなぜ好調に売れているのだろうか。
②海外のお守りがなぜ日本で流行するのだろうか。
この二つに関して祈願というキーワードを中心に、文献資料を主とし、一部アンケートと神社へのフィールドワークを行い調査した。また、近世以前の農耕社会、近世から広まっていった都市社会、戦後の現代社会という大きく分けた時代のなかで、行われてきた祈願の内容や方法を分析し、社会状況との関わりなどを考察した。
農耕社会の雨乞いなどの共同祈願が、都市社会化により願いが個人化していったことから減少し、個人祈願が増えていったように、祈願行為は社会や生活の形によって変化していくものである。
では現代に見られる祈願行為にはどのような社会や生活の状況が影響しているのだろうか。合格祈願の菓子商品を祈願として見ると、その特徴は「気軽さ」と「低コスト」である。普段の生活を外れず、特別なことを行わずに合格を祈願できる点が、効率を求める現代社会に受け入れられているのだろう。
また、海外のお守りやそれをモチーフとした商品が流行していることから、現代の日本人の特徴のひとつに、「効果があるといわれるモノを強くは疑わず取り入れる」という面が挙げられる。これは、古くから様々な祈願を行ってきたことや、異文化を巧みに取り入れる姿勢によると考えられる。
この基礎を持っていることで、生活の妨害にならなければ、新しいものもすぐに受け入れられ、冒頭の疑問である合格祈願商品や海外のお守りが流行するのだと考えられる。
貧乏神信仰の現在
財津 直美(東洋大学)
人々を貧乏にする神は「貧乏神」だと考えられている。日本民俗学では、厄神と福神を表裏一体の関係とする両義的な神観念があることが研究されてきた。こうした厄神信仰をふまえて、貧乏神を祀る神社の現地調査を行って事例を検討し、現代における貧乏神信仰の位置づけを考察したい。
「災禍転福貧乏神神社」(長野県飯田市大瀬木)は、祭主のS氏が自身の貧窮経験をもとに一九九八年に創建した貧乏神追放のための神社である。S氏は人間の禍福の原因を自助努力に求め、貧乏神は自分の弱い心の象徴であり、追放すべき存在だと解釈している。
しかし、実際に神社で行っている「神木を叩き、蹴り、豆を投げつける」という貧乏神退散の儀礼は、節分の鬼追いを連想させ、この神社の縁起は、疫神の詫び証文や退散令に通じる内容となっている。この神社には分社があり、この長野県茅野市の味噌蔵諏訪分社では、貧乏神追放後に鈿女神社に参拝して福を招き、東京都の亀戸分社では、貧乏神の兄弟が参拝者の貧乏を袋につめて持ち帰ってくれるとする。これらの分社では、厄と福の不可分性や貧乏神の両義性を示す伝承が発生している。
さらに、各神社の貧乏神の神像や亀戸分社の貧乏神兄弟の姿は、少なくとも近世初期に井原西鶴が著した『日本永代蔵』巻四「祈るしるしの神の折敷」(一六八八)の挿絵や、『梅津長者物語』に描かれた貧乏神までさかのぼることができるといえる。
このように、災禍転福貧乏神神社における貧乏神信仰は、一見すると合理的な解釈と個性的な発想に基づく流行的社会現象のように見られるが、実際には、従来の厄神信仰や貧乏神伝承に通じる要素が息づいている。こうしたことから、現在の貧乏神信仰は、過去からの伝承と決して無関係に成立しているわけではなく、それらの流れをふまえたうえに存在する民俗事象として位置づけることができる。
津軽における家の神-屋内神/屋外神をめぐって-
安藤 祐希(弘前大学)
屋敷神に関する研究は、直江廣治、岩崎敏夫、佐々木勝らの重要な研究があり、斉藤弘美がこれらを整理している。斉藤は、屋敷神研究は、起源や古態を探る研究から、屋敷神祭祀に現れる人々の社会関係の変化や、共同意識の差異を明らかにしてゆく方向に進むべきであるとしている。
本稿では、斉藤の提言を受けて、屋敷神という括りでは見えないものがあるのではないかと考え、家の神を屋内神、屋外神(いわゆる屋敷神)と捉えた。そして、両者を比較し、それぞれの動態を明らかにすることで、それぞれの位置や関係を探り、家の神がどのような形で共同性を帯びていくのかを明らかにすることを目的とした
調査地である青森県弘前市大沢は、主な生業を稲作とりんご栽培とする農村である。大沢では、屋内神も屋外神も「授かった」と称して祀り始めたり、アソバセルと称して霊場に運んだりすることがある。これらの現象は、屋内神の中では特にオシラサマにみられる現象である。オシラサマは、通常、屋内で祀られるものだが、積極的に外へ出ようとする性格をもつ神であると認識されている。また、屋内神、屋外神の祭祀には、指示や助言などのかたちで、民間宗教者が関与する場合が多い。
大沢の屋外神の多くは個別祭祀であるが、近隣の者が祭祀に参加するという形で共同性を帯びているものがある。またその祭祀場所は屋敷地と、家の耕作地がある。また、屋内神を屋外に移動させる場合もある。
これらの家の神を、祀る当の家の人と近隣の人々や集落の人々がどのように認識しているかを調査し、祭祀場所や祭祀集団の変化を検討することで、家の神が家の外に出て行くことが、共同性を帯びる契機となることを示した。
民俗芸能はだれのものか─宮城県旧秋保町「長袋の田植踊」を事例に─
沼田 愛(東北学院大学)
本稿では、宮城県旧秋保町において伝承されている「長袋の田植踊」(以下「田植踊」と記述)を事例として、演者に限らず日常生活をともに営む地域住民の視座をもとに、民俗芸能の伝承活動を捉えることを試みる。長袋町部落では「田植踊」をめぐる意識と伝承活動の実情が相反している。よって筆者は「田植踊をする」営みと実践する人びとを取り巻く住民の意識に焦点をあて、伝承活動の分析を行った。
昭和初期以前の「田植踊」は伝承することができる人物が限られた特権的なものであった。長袋町部落の契約講に加入できる家の中でも、更に特定の家が伝承者を輩出することで伝承されていたのである。
しかし戦後、人員不足により伝承者になる条件が緩和され、契約講の改新によって「田植踊」に対する発言権を持つ者が増加した。更に「田植踊」が宮城県および国から文化財の指定を受けたことにより、部落内の住民であれば「田植踊」に関与できるという正当性が生まれた。「田植踊」は部落の共有財産として認識されるようになったのである。
だが、現在では「田植踊」の伝承活動を中心的に行う保存会に参加する者は少人数である。伝承活動の詳細が多くの部落内の住民にとって不透明になり、住民の間で不和も生じている。踊りの指導の正当性が経験に基づく保存会に、「田植踊」との関係性を作り始めたばかりの住民が深部まで参加し続けることは非常に難しかった。住民たちは「田植踊」が「みんなのもの」になるという近代化の過程を共有したが、芸能を伝承してきた方法や経験はそれを完全に受け入れることができなかったといえる。
この事例は、民俗芸能の伝承活動が文化財指定という正当性を得て多くの住民に開かれることは可能であったが、その状況を維持することの難しさを示している。今後は「田植踊」を共有財産として認識させた民俗的背景をより多角的に踏まえることによって、地域社会を理解する一助になると考える。
大滝神社の「浜下り」の儀礼と組織
今村 瑠美(東北学院大学)
本報告でとりあげる「浜下り」について、『日本民俗大辞典』によれば、神体や神輿、あるいは人が海岸に出て、潮水を浴びる神事や行事のことで、これまでの研究では儀礼の意味を考えるものが中心で、儀礼の内容をおさえた上で、それを支えてきた組織にも注目し、後者を軸とした研究はほとんど行われていなかった。そこで本論では、福島県楢葉町の大滝神社で伝承されている「ハマクダリ」を対象に、儀礼の展開とともに、その組織の特徴についてもみていくことで、「浜下り」研究のみならず東北地方の民俗を考える上での新たな課題も提示したい。
本論で取りあげる大滝神社の「ハマクダリ」には、「小塙義団」と呼ばれている青年の組織がある。『大滝神社の浜下り神事―楢葉町無形民俗文化財調査報告書』によると、この組織は青年会に近い組織であるが、一般の青年団とは異なって行政的な役割はなく、純然たる祭典のための組織であると記されている。それに対して、一般的に呼ばれている青年団の多くは祭りの運営、執行の他に、冠婚葬祭の手伝い、消防などは行政的な役割を担っている。
より、「小塙義団」は一見、かつての若者組のようなものであるが、一つ一つの役割や活動内容に意味があり、それが祭りでは重大なもので、氏子総代が主体なっている祭りでも、日頃から信頼を築いてきている「小塙義団」がいないと祭りにはならないほどの大きな存在である。
ところで、この祭りを支えてきた中心となる組織である「小塙義団」の特徴として明治27年に成立したということである。その点からみれば近代においてこの祭りは再編成され、現在に至っていることが分かる。東北地方の民俗については一般的に古くから変わりなく受け継がれてきたかのようなイメージがあるが、実際に調査したところ、時代に合わせて大きく変化してきたようである。今後はこのような歴史的変化を踏まえた上で、民俗の特徴を考えていく必要がある。
年中行事における伝統と変容―正月を例に―
大貫 可奈子(首都大学東京)
変化の中で本来の行事の形を失いつつも、なぜ未だに年中行事は消滅することなく行われ続けているのだろうか。正月を例にとれば、「毎年正月を祝うか」という問いには9割以上が「祝う」と答える一方、「おせち料理は自宅で作らず既製品を購入する」「屠蘇は牛乳や麦茶で済ませる」など、元々の行い方や意味を考慮しないような行動が多く見られるようになっている。本来多くの年中行事は農耕と切り離せない関係にあり、年中行事を行うことは豊作を祈ると共に、自らの生活に安定をもたらすために重要なものであった。しかし近年、多くの人々は都会に住み、農耕とは無縁の生活を送っている。それにも関らず、なぜ現代日本において年中行事が継続して行われているのか。それを探ることが本論文の目的である。
論文では、正月という一つの年中行事を例にとり、文献資料と、筆者の出身地である多摩地域において行ったアンケート調査の結果(2009年11月~12月実施、84人からの回答)の2つの資料の分析を基に考察を行った。
その結果、現代における正月の存在理由は、①生活の折り目作りの手段、②個人の欲求を満たす手段、③コミュニケーション創出の場としての役割、④文化の記憶の影響、⑤商業主義の影響、の5点にまとめられた。またこの結果は正月行事だけではなく、日本の現代社会において依然伝承されている年中行事全体にも当てはめることが可能であると筆者は考えた。
現代において年中行事が行われているのは、先に挙げたような理由から、それが人々に必要とされているからである。農耕社会において行われていた年中行事と比較してみると、行い方やそれを支える要因には変容が見られるが、人々の生活に必要とされているものであるという伝統は未だ保たれている。このように人々に必要とされる限り、年中行事はその時々の状況に見合った形へと変化を遂げ、行い続けられていくのではないかと考えられる。